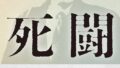出産やその場に立ち会った経験がある方は、
命を産みだす感動的な瞬間を目の当たりにしたことがあるでしょう。
私の長女はこれまでにラマーズ法で5回出産をしました。
私自身が、長女を生むとき、ラマーズ法のお産がいかに優れているかを
経験していました。
ラマーズ法の優れているところは、
呼吸法で産み出すため苦痛が小さい事です。
また、夫や家族が同伴する中で、出産の喜びを共有することができます。
そのために娘の5度目の出産に、家族全員が分娩室に入り、
出産に立ち会いました。
命が生まれるその瞬間は、
家族にとって特別で忘れられない経験となります。
分娩室の中の分娩台の上でも陣痛と陣痛の合間の時間は、
娘は子供達と笑ったり楽しそうにおしゃべりをしています。
これが今からお産をする妊婦の姿なのかと・・・
でも実際、命が生み出される時間は感動と喜びのセレモニーです。
中学生の孫は、分娩室内をウロウロしながら、
すべてが彼の興味深い研究対象のようです。
いよいよ出産のクライマックスの瞬間、
分娩室は、赤ちゃんの心音と娘の呼吸音と
助産婦さんの声掛けだけになります。
幼稚園児の孫はパパにしがみついていました。
しかし、その中で小学生の孫だけは目に涙を浮かべていました。
私が「怖い?」と聞くと・・・
彼は首を横に振り、じっと涙をこらえていました。
「君もそうやって生まれてきたんだよ」と彼の耳元でささやくと・・・
彼の小さな目から涙がポロポロとこぼれ落ちました。
その瞬間に、命の誕生がどれほど尊く感動的なものか、
孫を通して実感させられました。
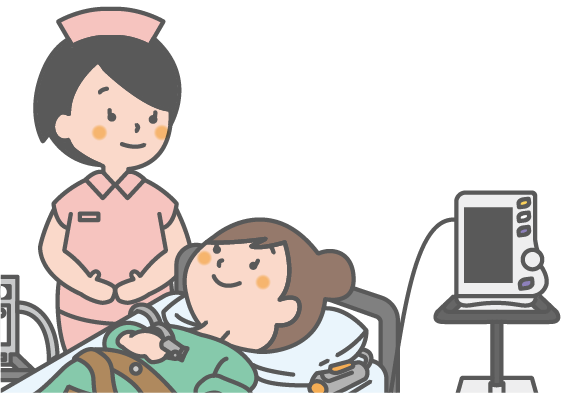
赤ちゃんとお母さんが共鳴する神秘な瞬間
やさしくライトアップされた分娩室の中にはさまざまな機械や装置があります。
その中でひときわ大きく響く音が、お腹の赤ちゃんの心音です。
赤ちゃんの心音は、分娩監視装置(NST)を通じて確認されています。
これは、お腹の中の赤ちゃんの状態を把握するための重要な「バロメーター」。
心音が一定のリズムを刻んでいることで、
赤ちゃんが元気でいることがわかります。
これから生まれてくる命の鼓動は、
家族の新たな絆を生み出す音でもあります。
この音を聞くことで、家族は赤ちゃんの存在をより身近に感じ、
出産の神秘と感動を深く味わうことができます。
特に立ち会う子どもたちにとっては、
命の尊さや家族のつながりを学ぶ貴重な機会となるのかもしれません。
新しい命を産みだす「啐啄同時(そったくどうじ)」
赤ちゃんがこの世界に生まれてくるためには、
子宮の収縮、いわゆる「陣痛」が必要です。
陣痛が始まると、子宮の収縮によって一時的に赤ちゃんに送られる血液の量が減少し、
赤ちゃんは酸欠状態の苦しい状態になります。
その結果、赤ちゃんの心音が速く、大きくなります。
陣痛はお母さんの痛みだけでなく赤ちゃんの痛みでもあります。
お母さんと赤ちゃんはお母さんの呼吸法で痛みを回避していきます。
「ドク、ドク、ドク・・・」
力強く響くその音は、赤ちゃんが一生懸命に外の世界へ向かっている証です。
お母さんは、この赤ちゃんの心音が速くなるタイミングに合わせ、
大きく深呼吸をし、全身で「いきむ」という動作を行います。
その呼吸といきみの力が合わさり、赤ちゃんは狭い産道を
回転しながら通過していきます。
赤ちゃんとお母さんは、まるで一つの生命体のように息を合わせながら、
この苦しく困難な瞬間を乗り越えていくのです。
お母さんと赤ちゃんの調和が生み出す神秘的な奇跡の瞬間・・・
それが出産です。
やがて、産声が響き渡り、赤ちゃんが自力で呼吸を始めた瞬間です。
まさに、赤ちゃんとお母さんが絶妙なタイミングで響き合う「出産」こそ、
「啐啄同時(そったくどうじ)」の象徴と言えます。
コロナ禍の頃の出産は分娩室には誰も入れず、
お母さんは一人で孤独に出産したと聞きました。
家族が出産に立ち会うという体験は、
改めて生命の尊さを感じ、家族の絆を実感させてくれました。
「啐啄同時」とは、雛が卵の殻を内側からつつく(啐)音と、親鳥がその殻を外側からつつく(啄)音が同時に共鳴することで新しい命が生まれる様子を表した言葉です。
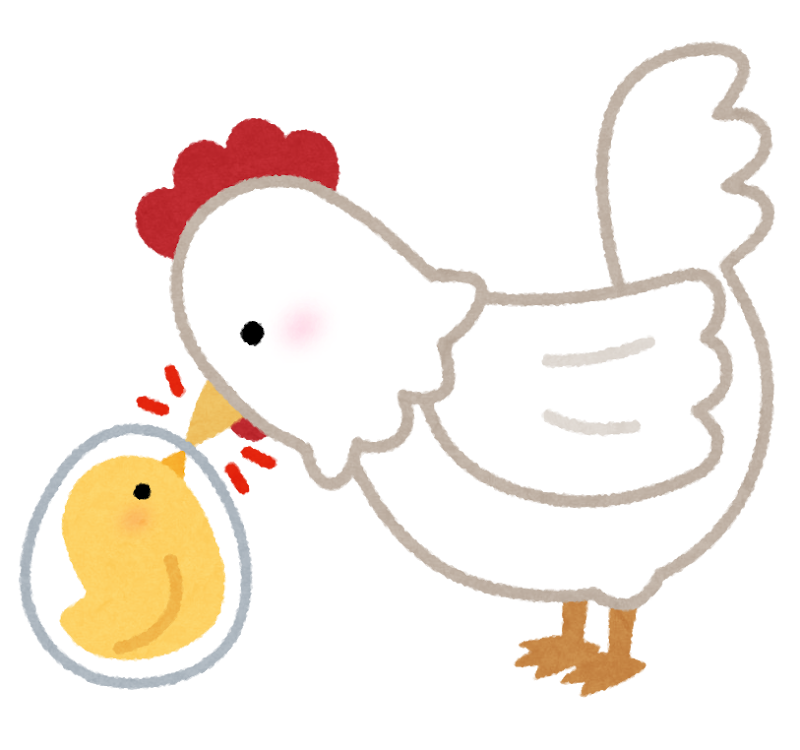
<☟写真は、4男の出産から退院時の様子>